東北大学大学院 学生員 ○早川 哲史
東北大学大学院 正 員 今村 文彦
東北大学大学院 正 員 牛山 素行
1. はじめに
津波防災対策においては,今後環境面あるいはコスト面を考慮して避難計画などを中心としたソフト面での対策を,従来行われてきた沿岸構造物の建設などハード面での対策と並行して整備していく必要がある.その際,特にソフト面での防災対策の効果や避難行動の将来予測を行うためには,災害経験に基づく災害知識や災害教育によって獲得される知識の向上,そして治水整備あるいは情報提供システムの整備などの変化を考慮する必要がある.そのためにはこのような災害に対する意識の変化と避難行動の開始に関する定量的な評価を行う必要がある.
今回は,津波避難に関するアンケート調査や津波防災ワークショップを実施し,その中で津波災害に対する意識や行動の変化をみていくことにする.
2. アンケート調査
2.1 避難行動の開始に影響する要因について
津波避難に関するアンケートは2000年7月より2002年10月までの間に計11回実施されており,回答数は1492である.質問項目として出身地,年齢,性別のほか津波に関する一般認識として津波の発生原因,沖合での津波の伝播速度,沿岸での津波の伝播速度の3つを設定している.また,海岸にいる場合の避難行動の開始段階,そして危険性を感じる津波の波高や海岸にいる場合に避難に要すると考えている時間を設定している.
ここでは避難行動の開始段階に関して,「年齢」,「性別」,「津波の発生原因」,「沖合での伝播速度」,「沿岸での伝播速度」,「危険を感じる波高」,「海岸にいる場合に避難に要すると考えている時間」との関連性について検討するために危険率を5%としてχ2検定を行った.その結果をまとめて表1に示す.なお,避難行動の開始段階については,表2に示すように3段階に設定する.ここで,周囲の行動を見て避難行動を開始するという回答は自主的な判断を行うことができないものと判断し,時間的に最も遅い「それ以降」に含めることとした.表1より年齢,津波の発生原因,沖合での伝播速度,沿岸での伝播速度,危険を感じる波高については避難行動の開始段階とのあいだに何らかの関係があることがわかった.一方,性別や避難にかかると考えている時間については避難行動の開始段階との関連性がみられなかった.
表2 避難行動開始段階の設定
2.2 比率の差の検定
続いて,ここでは津波の発生原因,沖合での伝播速度,沿岸での伝播速度,危険を感じる波高の4問について,正しい認識と間違っているものとに分類し,その正答数によって地震の発生や警報の発令に対してどの程度意識の変化が見られるのかについて検討を行った.津波の発生原因については「海底の地震や火山,地滑りによって発生する」,沖合での津波の伝播速度は「飛行機並(時速700km)」,沿岸での津波の伝播速度は「オリンピック短距離選手並(秒速10m)」がそれぞれにおける正答である.また危険を感じる波高については,ここでは津波強度・津波形態および津波に関する被害図(首藤,1993)より「2m」以下の回答について正しい認識であるとした.被害図によれば津波の波高が2mを超えると沖合で水の壁が発生したり,あるいは木造家屋や漁船に被害が発生したりする.
これら4問についてすべて回答しており,また避難行動の開始段階についても回答されている1126部を用いて,正答数別に避難行動の開始段階についてその割合をみることにする.なお,平均の正答数は2.21問であった.そこで,ここでは平均以上(3〜4問正答)と以下(0〜2問正答)における比較の結果を図1に示す.図1より,正答数の多い方が地震の発生という時間的に最も早い段階で避難行動を考える人の割合が多くなっていることがわかる.また,地震の揺れに対しては避難を考えないがその後の警報の発令に対しては避難行動を開始するという回答の割合についても正答数の増加に伴って大きくなっていることが確認できる.これらの比率の差(順に18.7%,10.0%)について危険率5%で検定を行った結果,いずれも有意な差となった.
このように,一般的な知識の増加によって地震の揺れや警報の発令に対する意識を高めることが可能であるということが確認できる.
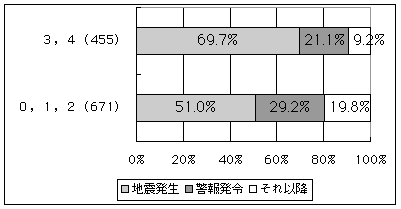
図1 正解数による避難行動開始段階の比較
表3 ワークショップの参加による意識の変化
防災マップを何度も見ている 21.4% 38.7% 14.4% 津波警報をラジオで聞いた場合に避難する 54.8% 74.2% 54.5% 自宅から避難先まで歩いて避難する 48.6% 66.7% 48.8% 地域の防災訓練に関心を持って参加している 42.1% 71.0% 18.2% 災害が起こったらどうするか家族と話をしている 36.8% 67.7% 31.4% 家の周りなどに危険な場所がないかチェックしている 27.3% 54.8% 18.2%
3. 津波防災ワークショップ
2002年10月から11月にかけて地震や津波に備えるために防災ワークショップが仙台市宮城野区中野の港町内会において3回にわたって開催された.第1回のワークショップの始めに参加者に対してアンケート調査を実施した.また,第3回のワークショップ終了後,あらためて「防災に関するアンケート調査」を実施して,このワークショップに参加した港町内会と隣接する蒲生町内会の各世帯に1部ずつ配布した.その際,ワークショップに参加した人としていない人,あるいは参加者の事前と参加後の意識の比較を行うことができるようにした.回答数は事前アンケートが44,事後アンケートが160であり,そのうち「参加した」という回答が31,「参加していない」という回答が121となっている.表3に危険率5%によるχ2検定の結果,防災ワークショップの参加に関連して変化したと考えられる項目を示す.表3より,ワークショップの参加によって防災マップの認識や地域の防災訓練に参加する,あるいは家族と話し合うというような普段の心構えから,津波警報に対する行動のような災害発生時の意識,さらには避難手段や危険箇所のチェックなど避難経路の選択まで全般にわたって意識の向上を確認することができる.
4. おわりに
Mileti & Sorensen(1987)によれば,警報に対する対応行動の流れは€聞く, 理解する,¡信じる,¤個人化する,¦決定する,©行動する,となっている.実際には,自分が持っている内的な情報と災害時に獲得した外部からの情報によって身の危険性について判断し,行動を開始するということが考えられる.ここでは,一般的な知識の向上によって避難に対する意識が高くなったということを示すことができた.さらに,地域における危険性についての意識を高めることによってより詳細かつ具体的な状況について考えることができ,適切な判断をとることができるものと思われる.
参考文献
首藤伸夫(1993):津波発生および来襲時の音響−その2 昭和三陸大津波による沿岸での音響発生条件−,津波工学研究報告,第10号,pp.1-12
Mileti, D., & Sorensen, J.(1987):Natural hazards and precautious behavior, Taking care, Chap.9, pp.189-207