1. はじめに
現在,津波対策としての防災施設,防災地域計画,防災体制を含めた総合的な 対策が研究されている.中でも津波予警報は防災体制の重要な要素であり,正確で適 切な予報ができ,伝達手段が完備されれば,人的被害,経済的被害の相当数を軽減で きるものと期待されている.そこで本研究では近年整備されつつある,海底津波計, ブイ型津波計などの海域津波計を用いて遠地津波を対象としたリアルタイム予警報の 可能性を検討する.
2. 想定津波の決定
想定津波は海域津波計の設置位置の決定,その後の波源域の推定 の際に利用する.初期条件を決める各断層パラメータを決定するために,過去90年に 環太平洋で発生した地震(Harvard Univ. Moment Tensor Catalog)と,環太平洋の沈み込み帯に関する研究(Pacheco,1993)より調べ,各地 の特徴を調べた.
Èメカニズム解の決定
その結果,走行,断層面の傾き,滑り角,震源深さには各地域に おいてある程度の関係があることがわかり,この関係から各パラメータを決定するこ とにした.
É他の断層パラメータ,地震の規模の決定
残る地震パラメータには,食い違い量,断層面面積,地震モーメ ントがあり,これらには次の関係がある.
ここで,Moは地震モーメント,μは震源域を構成する岩石の剛性 率,S は断層面の面積,D は食い違い量である.また,Dを決定する手段としてサイスミック・カップリング係 数αを用いた.αは沈み込みによる歪みエネルギー全体に対して地震により解放され るエネルギーの程度を表しており,次の関係式を考える事ができる.
ここで,Csはプレートの沈み込み速度,Trは地震発生間隔時間で ある.以上よりMoとDが推定されるので残りの断層面面積は(2.1)式を用いて求めることができる.
Ê想定津波の位置と個数
想定した位置と個数をFig.1に示す.位置と個数の決定の際,設置に偏りが出ないように注意を している.
3. 海域津波計の設置方法
海域津波計の設置位置としては,環太平洋で遠地津波がどこで発 生しても見逃さないような場所に設置しなければならない.そのためには断層短軸方 向に伝わる波を観測する必要がある.なぜなら,エネルギーの指向性より,短軸方向 に津波の多くのエネルギーが放出されるからである.そこで,想定した全断層から短 軸方向に波向線を描き,それを効率的に押さえるような位置を検討する.ここで用い る波向線法は李・他(1997)の研究を参考とした.
各92個の想定断層から短軸方向に波向線を放射するのであるが, 断層はある広がりを持つので,波向線の放出本数をどの程度用いれば適当であるかを 調べる必要がある.そこで,各92個の想定断層より,波向線をそれぞれ1,3,5本を 放出してその通過頻度を調べた.この結果,波向線3本が妥当であると判断でき,通 過頻度の高い地点に津波計を置くこととした(Fig.2参照). また,日本に対する津波到達時間と,津波計での津波観測時間の比較,すなわちリア ルタイム評価も行い,波源域推定の時間的余裕も確認した.
4. 波源域のリアルタイム推定
リアルタイムに津波波源情報を推定する際に最も難しいのが波源 域,つまり波源の広がりであり,ここではその推定の検討を行う.仮設した津波計で 得られる水位時系列よりわかる,津波到達時間を利用して,逆伝幡手法(石田ら, 1998)から波源域の推定を行う.
波源域の推定を行う際,逆伝播手法を用いるならば仮設した1地 域に対して1つの津波計では不十分である.従って 2個1組の測線とし,波源域の両端を推定できるように,2測線を仮設する事とした. そこでまず,想定断層1,16,22において波源の推定を試みた.その1つ,想定断層1 の逆伝播図をFig.3に示す.
図中の黒丸が津波計データから推定される波源域の一端であり, 波源域における波の源点となる.Fig.3より波源域の位置ははっきりとわかるが,断層長さ,断層幅といっ た波源域の広がりには,ややずれがあることがわかる.この原因としては,津波計( 臨時)測線において図中の黒丸である波峰線の交点が,求めるのが困難であった事が 考えられる.これは,アリューシャン列島の存在により,波向線が陸地で止まり,波 峰線がうまく描けなかったことにある.また,想定断層16,22の場合にもやや波源域 にずれがみられた.しかし,これらは主に時間的なずれであり,津波計での水位時系 列において第一波の到達時間の読みとりの際に原因があると思われる.すなわち,断 層規模が小さい場合や,短軸方向から津波計が外れた場所にある場合などで推定誤差 が大きくなると考えられる.
5. 結論
環太平洋に幾つかの津波計を仮設し,それらを用いたリアルタイ ムな津波情報提供の可能性を検討した.ここでは,波向線法を用いて,津波を観測す るために効率の良い津波計の位置を決定することができた.また,波源域の推定にお いても,最低2測線(4個)の津波計があればほぼ可能であることがわかったが,津波 計の位置に改良すべき点があることもわかった.今後は,環太平洋全域に仮設した津 波計での水位時系列を用いて,断層幅,断層長さ,食い違い量の決定法についても検 討したい.
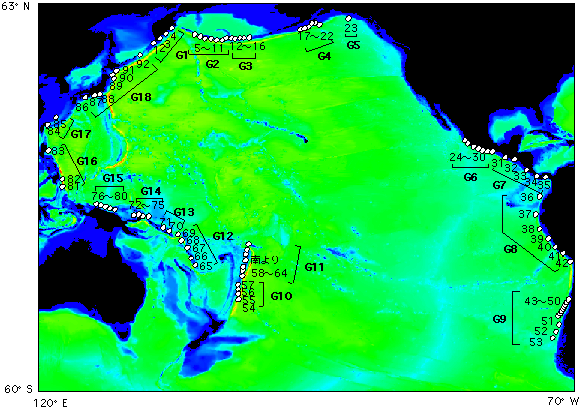
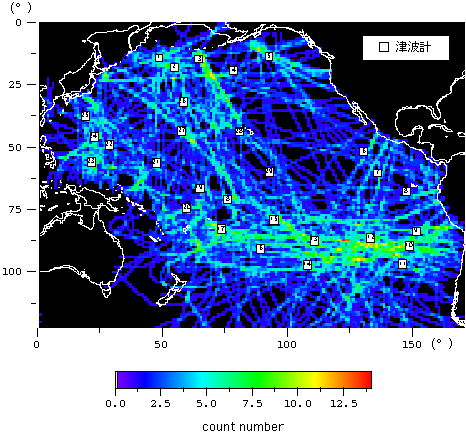
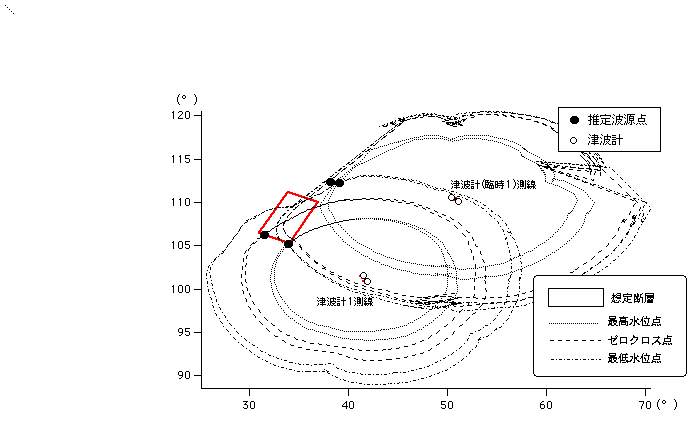
参考文献
1)F. Pacheco・他(1993):Nature of Seismic Coupling Along Simple Plate Boundaries of the Subduction Type,JGR, Vol.98,No.B8,pp14133-14158,1993
2)李昊俊・他(1997):屈折現象に注目した津波数値計算の精度,海 岸工学論文集,第44巻,pp.276-280,1993
3)石田祐介・他(1998):三陸沖での新しい監視方法による津波情報 提供の可能性,海岸工学論文集,第45巻È,pp386-390
