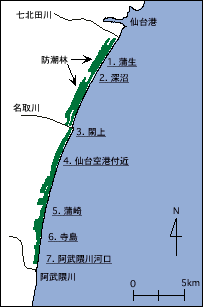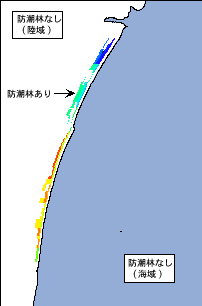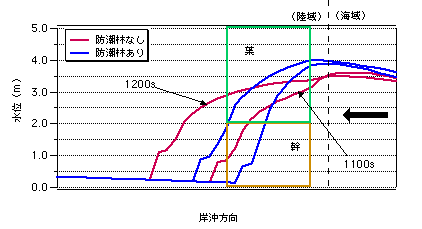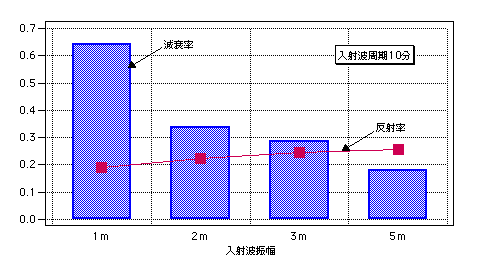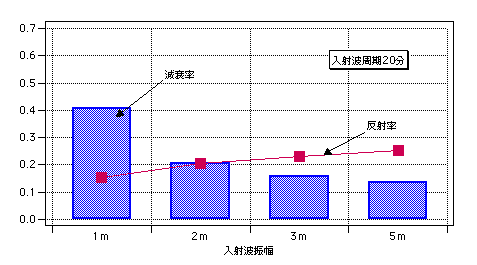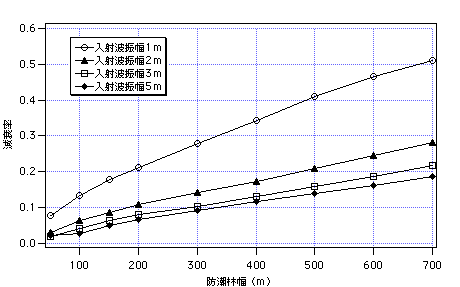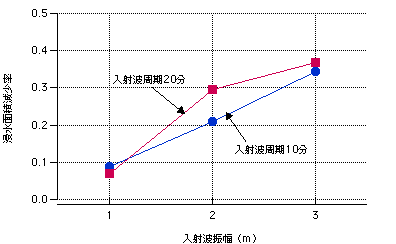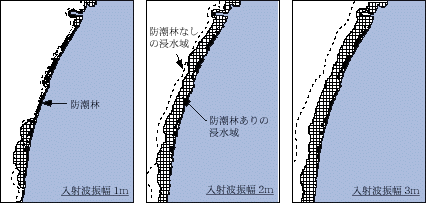1. 偼偠傔偵
丂捗攇偵懳偡傞杊挭椦偺岠壥偵偮偄偰偼丆庱摗1)偑夁嫀偺捗攇旐奞偺帠椺偐傜杊挭椦偺尭嵭岠壥傗尷奅傪帵偟偨偑丆掕検揑側崻嫆偵婎偯偄偨媍榑偼側偝傟偰偄側偐偭偨丏偦偙偱丆杮尋媶偱偼丆愬戜榩増娸偺杊挭椦傪懳徾偵尰抧挷嵏傪峴偄丆尰抧偱偺杊挭椦偺掞峈傪儌僨儖壔偟丆偳偺掱搙偺捗攇偵懳偟偰偳偺傛偆側掅尭岠壥傪桳偡傞偺偐偵偮偄偰丆悢抣寁嶼傪傕偲偵専摙傪峴偆丏
2. 杊挭椦儅僢僾偺嶌惉
2.1 奣梫
丂悢抣寁嶼儌僨儖偵杊挭椦偺岠壥傪摫擖偡傞偨傔偵偼丆廬棃偺儌僨儖偵巊傢傟偰偄傞抧宍僨乕僞偵壛偊偰丆杊挭椦偺枾搙丆怉惗丆攝抲丆柺愊側偳偵娭偡傞僨乕僞偑昁梫偱偁傞丏峀堟偵傢偨傞杊挭椦傪懳徾偵偙傟傜偺忣曬傪摼傞偙偲偼崲擄側偨傔丆尰抧挷嵏偲峲嬻幨恀傪慻傒崌傢偣偰杊挭椦偺忣曬傪摼傞偙偲偲偟偨丏
2.2 尰抧挷嵏偲峲嬻幨恀偺棙梡
丂挷嵏偼恾亅侾偵帵偡俈偐強偱峴偭偨丏偙傟傜偼杮懳徾椞堟偱偺怉惗偵偮偄偰偺戙昞揑側抧揰偱偁傝丆偙偙偱摼傜傟偨彅尦傪棙梡偱偒傞丏偨偩偟奀娸慄偲捈峴偡傞曽岦偵傕怉惗偑曄壔偟偰偄傞偨傔丆奀娸慄傊岦偐偭偰傎傏摍娫妘偛偲偵俀乣係抧揰偱應掕傪峴偆偙偲偲偟丆崌寁19抧揰偲偟偨丏應掕崁栚偼丆(1)姴偺廃挿丆(2)100m2拞偵懚嵼偡傞姴偺杮悢(枾搙乯丆(3)庽崅丆(4)梩偺枾搙偱偁傞丏(1)丆(2)偼捈愙應掕偡傞偙偲偑偱偒傞丏(3)偼捈愙應掕偡傞偙偲偼擄偟偄偺偱儗乕僓乕嫍棧寁傪梡偄偰捀晹偲梩晹傑偱偺崅偝傪偦傟偧傟應掕偟偨丏(4)偵偮偄偰偼僨僕僞儖僇儊儔偱嶣塭偟偨梩偺夋憸傪丆梩傪崟丆偦傟埲奜傪敀偵俀抣壔偟偰搳塭柺愊斾傪媮傔丆偙傟偐傜枾搙傪悇掕偟偨丏偙偺傛偆偵偟偰應掕偟偨奺抧揰偛偲偺暯嬒抣傪嶼弌偟丆偦偺抧揰偺戙昞抣偲偟偨丏傑偨丆杊挭椦暆丆掦慄偐傜偺嫍棧傗埵抲側偳偺忣曬偼尰抧偱摼傞偙偲偼擄偟偄偺偱峲嬻幨恀乮弅広丗1/8000丆1998擭3寧嶣塭乯傪棙梡偟偨丏
2.3 杊挭椦儅僢僾偺嶌惉曽朄
丂傑偢丆峲嬻幨恀偐傜媮傔偨杊挭椦偺忣曬傪傕偲偵杊挭椦傪暆丆宍忬側偳偑椶帡偟偨43偺嬫娫偵暘妱偟丆恾亅侾偺傛偆偵寁嶼奿巕偛偲偵杊挭椦偁傝丒側偟偺偄偢傟偐偺抣傪擖傟偨僨乕僞傪嶌惉偟偨丏崟偼杊挭椦偑懚嵼偡傞椞堟傪昞偡丏偝傜偵丆昁梫偲偝傟傞杊挭椦儅僢僾偲偼丆杊挭椦偑懚嵼偡傞斖埻偵尰抧挷嵏傪峴偭偨19抧揰偵懳墳偟偨忣曬傪擖傟偨傕偺偱偁傞丏尰抧挷嵏傪峴偭偰偄側偄応強偱偼尨懃揑偵嵟傕嬤偄抧揰偺戙昞抣傪梡偄傞偙偲偲偟丆怉惗偑戝偒偔曄傢傞傛偆側偲偙傠偱偼椶帡偟偨怉惗忬懺傪傕偮抧揰偺戙昞抣傪慖傫偱偦偺僨乕僞傪梌偊偨丏杊挭椦儅僢僾傪恾亅2偵帵偡丏
3. 杊挭椦偺悢抣儌僨儖
丂 杊挭椦偺岠壥傪儌僨儖偵庢傝擖傟傞偨傔丆寁嶼偼愺悈棟榑幃偺塣摦曽掱幃偵杊挭椦偺掞峈傪昞偡崁傪晅壛偟偨傕偺傪梡偄傞丏傑偨熻忋寁嶼傕峴偆丏杊挭椦偺掞峈偼姴偲梩偺晹暘偱戝偒偔堎側傞偱丆暘妱偟偰峫偊傞傕偺偲偡傞偲丆x曽岦偺扨埵懱愊偁偨傝偺掞峈Fx偼儌儕僜儞幃偵側傜偄丆師偺幃(1)偺傛偆偵昞偡偙偲偑偱偒傞丏
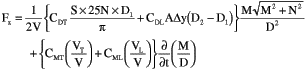
| (1) |
偙偙偱丆CMT, CML丗姴丆梩偺晅壛幙検學悢2)丆CDT, CDL丗姴丆梩偺掞峈學悢2)丆V丗悈偺晹暘偺懱愊丆VT丗姴偺懱愊丆VL丗梩偺懱愊偱偁傞丏y曽岦偺掞峈Fy偵偮偄偰傕摨條偵峫偊傞丏傑偨丆D1 ,D2偼慡悈怺D偲栘偺崅偝偺娭學偐傜丆
乮叧乯丂D1= H1丂丆D2= H2 丂乮D亞H2乯
乮叴乯丂D1= H1丂丆D2=D 乮H1亙D亙H2乯
乮叺乯丂D1=D2=D丂丂丂丂丂丂 乮D亝H1乯
偺俁偮偺応崌偵暘偗傜傟傞丏H1丗梩晹傑偱偺崅偝丆H2丗捀晹傑偱偺崅偝傪堄枴偡傞丏VT /V丆VL/V偼丆尰抧挷嵏偱摼傜傟偨庬乆偺應掕抣傪梡偄偰昞偡偙偲偑偱偒丆幃(2)偺傛偆偵側傞丏

| (2) |
4. 悢抣寁嶼寢壥偲峫嶡
4.1 儌僨儖抧宍偱偺寁嶼忦審
丂偙偙偱偼丆傑偢丆懳徾椞堟偵偍偗傞侾師尦娸壂曽岦偵丆愬戜榩偺暯嬒揑側抧宍岡攝傪傕偮儌僨儖抧宍偱偺悢抣寁嶼傪峴偄丆杊挭椦偺暆傗擖幩捗攇崅偝偵傛傞岠壥傪挷傋偨丏杊挭椦偺暆偼50乣700m偺9庬椶偲偟偨丏杮懳徾椞堟偱50m偼嵟掅丆700m偼嵟崅偺杊挭椦暆偱偁傞丏檛懁偺擖幩忦審偲偟偰廃婜10暘丆怳暆2m,5m,10m偺sin攇傪梌偊偰偄傞丏傑偨丆杊挭椦偺僨乕僞偼丆愬戜榩増娸偵偍偗傞杊挭椦偺暯嬒揑側僨乕僞偲偟偰丆庽崅偼捀晹10m丆梩晹5m乮偨偩偟丆嵟傕奀娸慄偵嬤偄儊僢僔儏偱偼捀晹5m丆梩晹2m偲偟偨乯丆姴偺廃挿50cm丆侾儊僢僔儏偁偨傝偺庽栘偺杮悢825杮丆梩偺搳塭柺愊斾0.65傪壖掕偟偰偄傞丏側偍丆梩偲姴偲傕偵晅壛幙検學悢2.0丆掞峈學悢1.0傪壖掕偟丆Manning偺慹搙學悢偼0.025偲偟偨丏
4.2 儌僨儖抧宍偱偺寁嶼寢壥
丂傑偢杊挭椦晅嬤偺攇宍偵偮偄偰徻偟偔尒傞偨傔偵丆杊挭椦偵捗攇偑摓払偟偨捈屻偺悈埵偺嬻娫暘晍偵偮偄偰恾亅3偵帵偟偨丏擖幩攇偺怳暆2 m丆廃婜20暘偺応崌偱偁傞丏偙偺恾傛傝丆杊挭椦偑偁傞応崌偵偼杊挭椦庤慜偱悈埵偑忋徃偟丆撪晹偱偼偟偩偄偵掅壓偟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丏傑偨1100s偲1200s偺攇宍傪斾傋傞偲丆杊挭椦偵摓払偟偨捈屻偺1100s偺曽偑撪晹偱偺尭悐偑戝偒偔側偭偰偄傞丏偙傟偼丆攇偺愭抂偱偼棳懍偑戝偒偔側偭偰偄傞偨傔丆庽栘偵徴撍偡傞嵺偵幐傢傟傞僄僱儖僊乕偑戝偒偄偙偲偑尨場偱偁傞偲峫偊傜傟傞丏師偵杊挭椦庤慜偱偺斀幩棪偲捠夁屻偺怹悈怺偺尭悐棪偵偮偄偰擖幩攇怳暆暿偵傒偨傕偺傪恾亅4丆恾亅5偵帵偡丏偙傟傜偺恾傛傝擖幩攇怳暆偑戝偒偔側傞偵偮傟偰斀幩棪偑憹偟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丏偙傟偼杊挭椦庤慜偱偺悈怺偲梩丒姴偺崅偝偺娭學偵傛傞傕偺偱偁傞丏偮傑傝丆擖幩攇怳暆1m偱偼姴偵傛傞斀幩偺傒偱偁傞偑怳暆偑戝偒偔側傞偵偮傟偰梩晹偱偺斀幩偑晅壛偝傟傞偐傜偱偁傞丏偟偐偟丆庱摗1) 偵傛傞偲杮寁嶼偱愝掕偟偨捈宎栺15 cm偺庽栘偺応崌丆杊挭椦庤慜傑偨偼撪晹偺怹悈怺偑偍傛偦5 m偺捗攇偵懳偟偰偼愗抐傗搢栘偵傛傝柍岠壥偱偁傞偙偲偑帵偝傟偰偄傞丏傑偨丆挿廃婜偺20暘偺曽偑尭悐棪偼彫偝偔側偭偰偄傞丏師偵丆杊挭椦暆偵傛傞攇崅偺尭悐岠壥偵偮偄偰傒傞偲丆恾亅6偺傛偆偵杊挭椦暆偲丆怹悈怺偺尭悐棪偵偼傎傏斾椺娭學偑偁傞偙偲偑傢偐偭偨丏
4.3 幚抧宍偱偺寁嶼寢壥
丂偙偙偱偼丆幚嵺偺抧宍僨乕僞偲杊挭椦儅僢僾傪梡偄偰丆懳徾椞堟偵杊挭椦偺悢抣儌僨儖傪揔梡偟偨丏怹悈柺愊偼杊挭椦偺桳柍偵傛傝恾亅7偺傛偆偵曄壔偟偨丏偙傟偼擖幩攇廃婜10暘偺応崌偱偁傞丏慡懱揑偵偼尭彮偡傞偑丆抧宍傗怉惗忬懺側偳偺塭嬁偵傛傝嬊強揑偵棳傟偑廤拞偟丆杊挭椦偑側偄応崌傛傝傕怹悈堟偑峀偑傞偲偙傠傕尒傜傟偨丏擖幩攇怳暆丒廃婜暿偵傒偨怹悈柺愊偺尭彮棪傪恾亅8偵帵偡丏恾亅8傛傝擖幩攇怳暆偑戝偒偔側傞偵偮傟偰怹悈柺愊偺尭彮棪傕戝偒偔側傞孹岦偑尒傜傟丆椺偊偽丆3 m擖幩崅偺捗攇偵懳偟偰偼丆3乣4妱偺怹悈柺愊偺尭彮偑尒傜傟偨丏
5. 偍傢傝偵
丂杮尋媶偱偼丆尰抧偱偺杊挭椦偺掞峈傪儌僨儖壔偟丆悢抣寁嶼傪峴偆偙偲偵傛傝丆怹悈怺傗怹悈柺愊偺尭彮検傪嶼掕偡傞偙偲偑偱偒丆杊挭椦偺掕検揑側掅尭岠壥偵偮偄偰偁傞掱搙専摙偡傞偙偲偑偱偒偨丏
嶲峫暥專
- 庱摗 怢晇丗杊挭椦偺捗攇偵懳偡傞岠壥偲尷奅丆奀娸岺妛榑暥廤丆戞32姫丆pp.465-469丆1985丏
- 栰楬 惓峗丒崱懞 暥旻丒庱摗 怢晇丗捗攇愇堏摦寁嶼朄偺奐敪丆奀娸岺妛榑暥廤丆戞40姫丆pp.176-180丆1993丏
- 搚栘尋媶強丗杊嵭庽椦懷偺斆棓棳惂屼岠壥丆搚栘尋媶強帒椏3538崋丆104p丆1998丏
- Hamzah.L丆K.Harada and F.Imamura丗Experimental and numerical study on the effect of Mangrove to reduce Tsunami丆搶杒抧堟嵭奞壢妛尋媶丆戞35姫丆pp.127-132丆1999丏